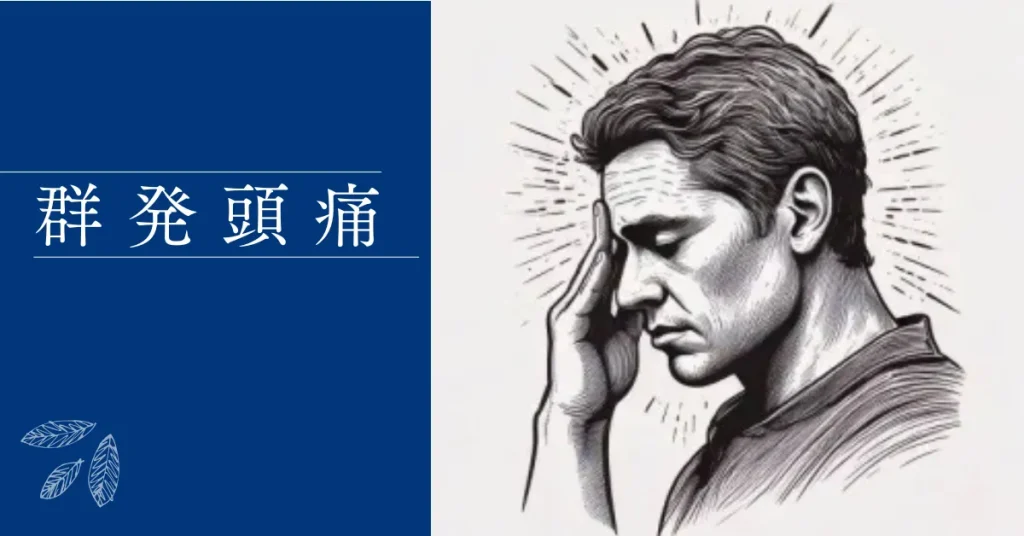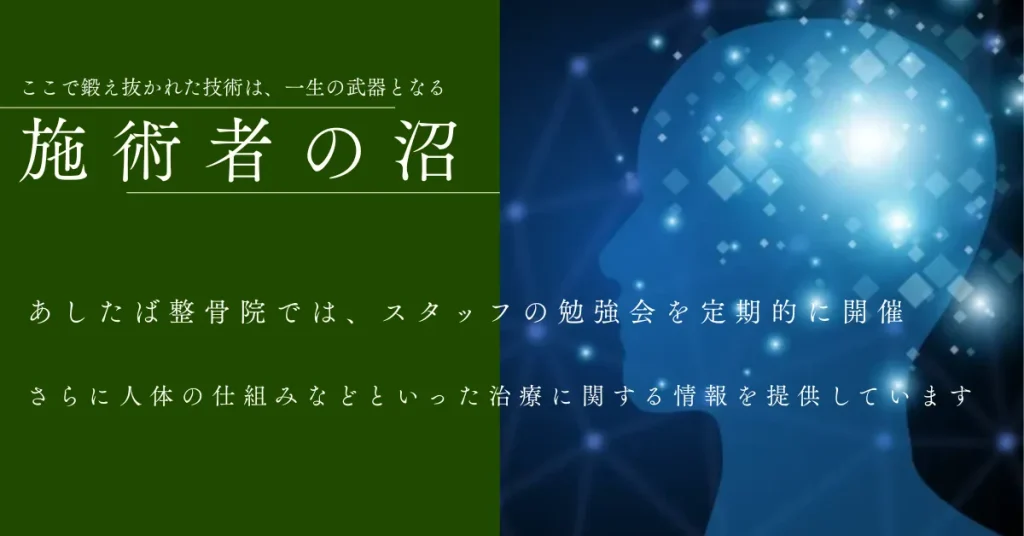概要(要点)
牽引は「機械的に椎間を離開して神経圧迫を一時的に軽減する」作用機序を持ち、頚部では選択的に短期的な症状改善が期待できるが、根拠は質的に限定的である。
腰部牽引については、ランダム化比較試験の総括や主要ガイドラインで「慢性・亜急性腰痛に対する有効性は示されていない/推奨されない」と明記されている。
しかし、臨床では「神経根症(radiculopathy)が明確な患者」や「急性の椎間板突出で明らかな神経圧迫が疑われるケース」に対して、短期の症状緩和手段として用いられることがある(患者選択性が鍵)。
以下、詳述します。
1) 牽引の生理・機序(なぜ効くことがあるのか)
椎体の離開(distraction)により椎間孔(foramen)面積が増加し、神経根への圧迫が物理的に減る。 MRIや生体力学研究で牽引による椎間孔・椎間高の増大が報告されています。これが神経圧迫由来の痛みに対する即時的な改善を説明します。
椎間内圧(intradiscal pressure)の低下:牽引は一時的に椎間内圧を減少させることで,突出した髄核の後方への張力を減らし(negative pressure の報告あり)、神経根への機械的負荷と炎症を下げる可能性があります。
筋緊張の軽減・循環改善:牽引で筋の緊張が緩み、局所血流/vasa nervorum が改善して疼痛閾値が下がることも想定されます(臨床での短期有益の一因)。
2) 頚部牽引(cervical traction)の臨床的意義
エビデンスまとめ
メタ解析・RCT のレビューでは 頚椎神経根症(cervical radiculopathy)や頚部の神経症状を有する患者群で、牽引(特に間欠的牽引や回旋-牽引併用)が短期的に痛み・機能を改善する結果があるが、対象試験数は少なく・研究質はばらつきがあり長期効果は不確かという評価が多いです。
臨床ガイドラインや保険方針では「初期治療の第一選択にはしないが、保存療法を行っても改善しない場合や手術を望まない/待機する患者に対しては妥当な代替として考慮されうる」とする記載が見られます。
臨床的示唆(適応・選択基準)
より期待できる群:明確な放散痛/神経根症状(絞扼による電気的痛み・筋力低下があるケース)、短期的な除圧で症状が軽減することが予想される患者。Physio-pedia のCTR(臨床予測ルール)などで“牽引に反応しやすい特徴”が提案されています。
短期的改善を目的に用いる:痛みの即時緩和、握力やバランスなど機能改善の短期効果を期待する場面に向く(複数の小規模RCTで即時効果報告あり)。
実践的パラメータ(研究でよく用いられている例)
牽引力:初期 = 5–12 kg(体重の約7–10%が目安とされる研究が多い)。高荷重は不快感を生むため漸増する。
モード:間欠的(intermittent)が持続牽引より患者許容性と効果面で有利とする報告あり。
時間:1セッション10–20分を1日〜数回/週でプロトコル化されることが多い(各研究で差あり)。
3) 腰部牽引(lumbar traction)の臨床的意義
エビデンスまとめ
総合的なレビュー(Cochrane 等)や主要ガイドラインでは、亜急性〜慢性の非特異的腰痛に対しては牽引の臨床的有効性は示されておらず、推奨されない/効果はほとんどないと結論付けられています。複数の高品質ガイドラインも同様の立場です。
一方で、特定の神経根症(急性の腰椎椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛)に対して、短期的な症状軽減を示す小規模研究や臨床報告が存在します。ただしRCTの結果は一貫せず証拠は不確かです。
実践的パラメータ(理論的基準)
牽引力:実際に椎体分離(真の椎間離開)を起こすには体重の 40–50% 程度(摩擦無し条件で)が必要との報告がある一方、筋緊張除去や軟部組織伸展を目的とする場合は 25% 前後でも用いられる等、用途で幅がある。
時間:20–30分が多数の研究で用いられるが、機器・体位(仰臥位/俯臥位・膝屈曲等)・モードにより差が大きい。
臨床的示唆
一般的推奨:非特異的腰痛や慢性腰痛には牽引をルーチンで使うことは推奨されない。代わりに運動療法・教育・認知的介入・合併症除外が優先される。
例外的活用:椎間板ヘルニアで手術回避を目指す短期的な除圧目的、または一時的な神経症状緩和を試みる場面での adjunct としての使用は臨床で行われるが、効果は個別差が大きい。
4) 患者選択と安全性(臨床上の注意点)
適応(一般的な目安)
明らかな神経根症状(頚部:放散痛・感覚異常・筋力低下)→ 頚部牽引は短期的に有益なことがある。
腰椎では「強い神経根症(急性のヘルニア)」で“短期的除圧”を狙う場合は検討されるが、試みる際は慎重なモニタリングが必要。
禁忌・注意(必ず確認)
骨折・感染・腫瘍・不安定性(外科的適応)や高度の骨粗鬆症、重度の椎間孔狭窄で牽引が危険なことがある。ガイドラインの「red flags」を必ずチェック。
血行動態の不安定、深刻な神経学的欠損(急速進行する麻痺)では牽引は不適。
不快感や症状増悪があれば直ちに中止する。
5) 臨床への落とし込み(スタンダードな現場プロトコル例)
(頚部)
1. 事前評価:神経根症の有無、筋力・反射・感覚、red flags を確認。
2. 初回は低負荷(体重の5–7% あるいは 5–8 kg)で短時間(10分程度)。患者反応を評価。
3. 効果があれば間欠牽引(例:50秒牽引:10秒休止など)を複数回/週で継続、症状や機能の改善を評価。
(腰部)
1. まずは運動療法・教育・活動改善を優先。牽引は「補助的選択肢」として位置付ける。
2. 使用する場合は明確な目標(短期除圧・痛み軽減)、適切な牽引力(臨床目的に応じ25%前後〜十分な分離を狙う場合は更に高負荷)が必要で、常に患者反応を監視。
6) 要約 — 現時点での“実務的結論”
頚部牽引:神経根症の短期的改善には“用いる価値がある”が、長期的効果・エビデンスの質は限定的。患者選択(radiculopathy 等)と適切なパラメータ設定が重要。
腰部牽引:非特異的腰痛では一般推奨されない。神経根症や急性椎間板ヘルニアなどの“選ばれた患者”に対して短期的な除圧目的で試みられることはあるが、ガイドラインは慎重。
どちらも 「機序的には合理的(foraminal widening, intradiscal pressure reduction)」 が、臨床効果は患者サブグループ・プロトコル・評価の違いで大きく左右される。