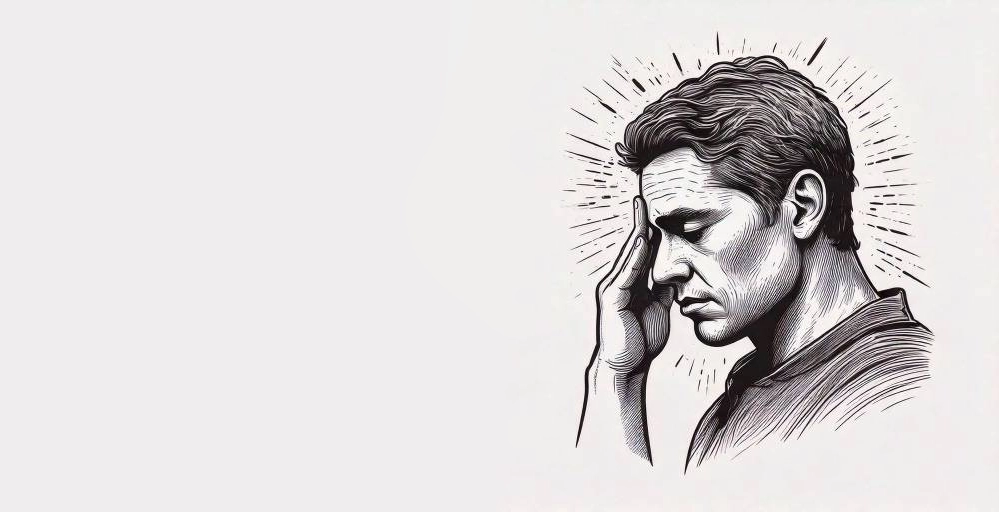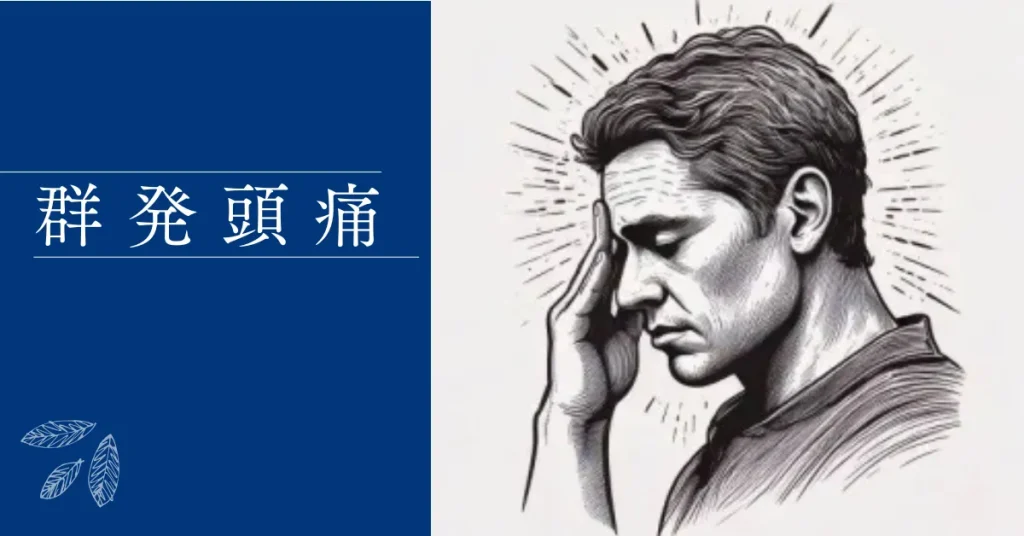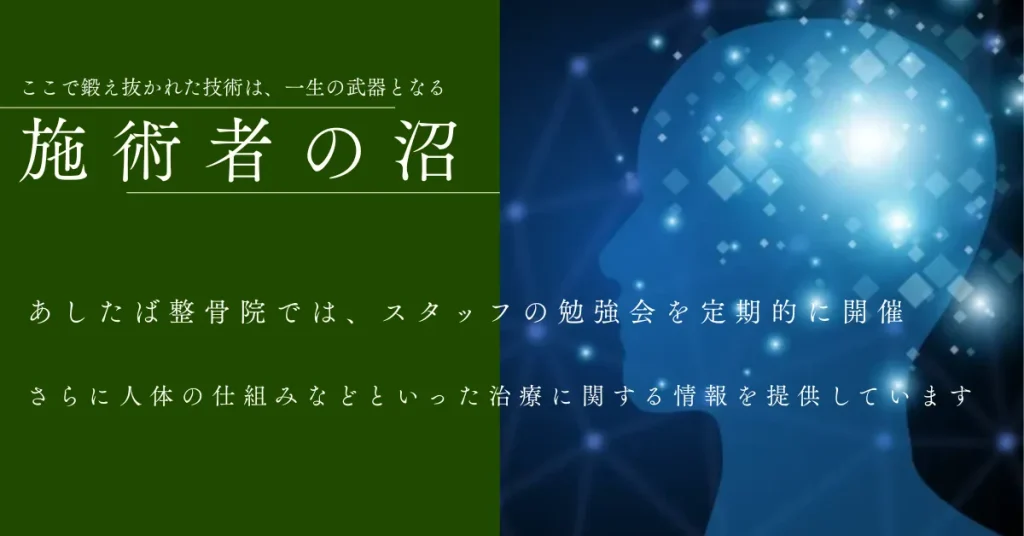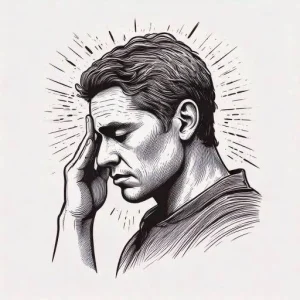なぜ群発頭痛は
頭痛薬や消炎鎮痛剤が効きにくいのか
群発頭痛は「自殺頭痛」とも呼ばれるほど激烈な痛みを伴いながら、一般的な頭痛薬や消炎鎮痛剤がほとんど効果を示さないことが特徴です。
その理由のひとつとして、群発頭痛の発生に物理的な神経絞扼(締め付け・圧迫)が関与している可能性が考えられます。
とくに、三叉神経や迷走神経といった脳神経が、環椎後頭関節や上位頚椎の歪みにより持続的に圧迫されるケースです。
物理的な絞扼には薬が効きにくい
物理的に神経が締め付けられている状態では、いわゆる「化学的な鎮痛アプローチ」である薬(NSAIDsやロキソニン、アセトアミノフェンなど)は、十分な効果を発揮しにくくなります。
例えば
例えば、「靴ひもが足の甲を強く締め付けていて痛みが出ている」状態を想像してください。
このとき、痛み止めを飲んだとしても、靴ひもをゆるめなければ痛みは続きます。
群発頭痛も、神経が骨格の歪みによって締め付けられている状態だと考えられ、同じく「薬では緩和しにくい」タイプの痛みといえます。
整体による改善の可能性と根拠
整体では、関節の歪みやねじれを整えることで、神経の通り道(関節間スペースや椎間孔など)を解放することができます。
とくに、環椎後頭関節の歪みを調整することで、三叉神経系や迷走神経系への圧迫を軽減できる可能性があります。
これは、前述の例でいえば「靴ひもをゆるめること」に相当し、神経そのものへのストレスを取り除く物理的アプローチです。
結果として、薬が効きにくい神経性の激痛も、整体によって圧迫が解消されれば症状が軽減・改善する可能性が高くなります。
対比:薬が効く頭痛のメカニズム
一方で、緊張型頭痛や軽度の片頭痛などは、筋肉の疲労や血管の収縮拡張による化学的反応が主な原因とされています。
これらは薬剤によって抑制できるため頭痛薬の効果が出やすい傾向にあります。
したがって、以下のように分類分けができます。
スクロールできます
| 薬が効く頭痛 | 化学的な炎症や血流異常が原因のもの | 例)緊張性頭痛、軽度の片頭痛など |
| 薬が効きにくい頭痛 | 物理的圧迫や神経絞扼が原因のもの | 例)群発頭痛など |
|---|
まとめ ~消炎鎮痛剤や頭痛薬の効果~
- 群発頭痛は、**脳神経への物理的圧迫(絞扼)**が背景にあるため、薬が効きにくい。
- 例えるなら、靴ひもで締め付けられている痛みには、靴ひもをゆるめない限り薬は無力。
- 整体では、関節の位置を整え、神経への物理的圧力を解放することができるため、改善が見込める。
- 一方で、薬が効く頭痛は化学的な反応が原因のため、対応アプローチが異なる。