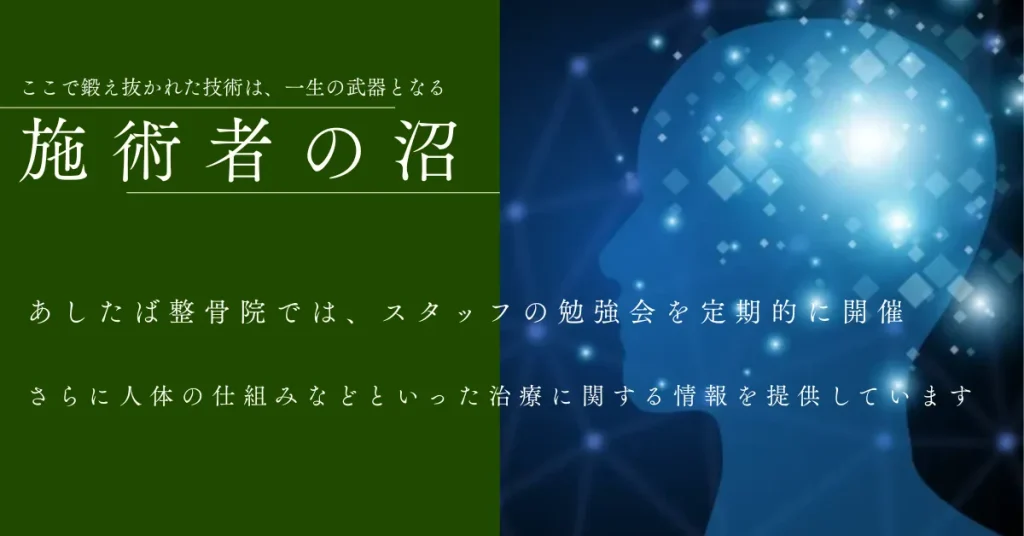わかってくれる人がいた。わかってもらえない場所もあった
分院での施術が軌道に乗り、来院者数も右肩上がり。
頭痛の改善という自身の“革命”を経て、久保の施術には明らかな変化が生まれていた。
カイロプラクティック、SOT、鍼灸、あん摩、それらすべてを融合させ、「本当に効く」治療を模索する日々。
その中心にあったのは、自らの身体で実証した手法と、何より“絶対に治す”という信念だった。
だが、その信念を支えていたのは、決して久保ひとりの力ではなかった。
静かな実験場
最初の協力者は、身近な存在だった。
実の妹――彼女もまた、体質的に不調を抱えることが多く、久保が試作する施術の“実験台”として、幾度となく身体を貸してくれた。
「ちょっと試させてくれる?」
「うん、いいよ」

何度も繰り返されたそんなやりとりの中で、久保はある仮説にたどり着く。
「血縁関係にある者は、からだのねじれや歪みの方向に一定の規則性があるのではないか」というものだった。
これは後に、彼の施術理論の大きな柱のひとつとなっていく。
もうひとりの協力者は、地元の先輩である大井さんだった。
久保がまだ鍼灸師としての感覚を手探りしていた頃、彼は毎週のように身体を提供してくれた。
久保の興味は、単に「ツボに刺す」鍼ではなかった。
筋膜の構造、細胞間の電気信号、皮膚と筋膜の間に走る微細なテンション――
それらを解放するには、鍼を筋膜と筋膜の“隙間”に刺す角度と深度が決定的に重要だと感じていた。
「ううっ……これ、けっこう響くね」
「ごめんなさい。でも、今の角度で“抜け”があったんです」
鍼が深く“当たる”と、患者は「ズーン」とした重たい感覚に襲われる。
それでも大井さんは文句ひとつ言わず、付き合い続けてくれた。
久保の中で、科学では拾いきれない感覚の輪郭が、少しずつ明らかになっていった。
組織という壁
だが、順風満帆だった分院長としての日々は、ある出来事をきっかけに暗転する。
ある日、常連の患者が本院にこう伝えたのだ。
「分院ではこんな治療をしてもらえる。本院でもやってほしい」
それは、ただの何気ない一言だった。
患者に悪意はない。むしろ、良くなったことを喜んでの言葉だった。
しかし、それが組織の“枠”を揺るがした。
久保の施術は、本院の方針とは異なる“独自の理論”に基づいたものだった。
ルールから外れた行動は、組織の秩序を乱す行為に他ならない。
そのとき、久保は理解できなかった。

「患者さんが良くなって、喜んでいるのに、なぜ責められるのか?」と。
後になって、経営というものを学んでようやく気づいた。
組織には組織の理念があり、方法の統一がある。
「正しさ」には、複数の種類がある。
そのとき久保は、治すことが“正義”だと思い込んでいた。
譲れない理屈だった。だが、経営者にもまた、譲れない理想があった。
院長は、久保を手放したくはなかったという。
それでも、両者の信念は交わらなかった。
それは、譲るべきではない“理念”の衝突だった。
そして久保は決めた。
「自分は、妥協せずに“絶対に治す”ことに重きをおいて生きていく」と。
そのとき、背後でひとつの扉が静かに閉じ、
同時に――もうひとつの扉が、音もなく開いた。
独立、そして開業――。
久保は、次のステージへと歩を進めることとなる。