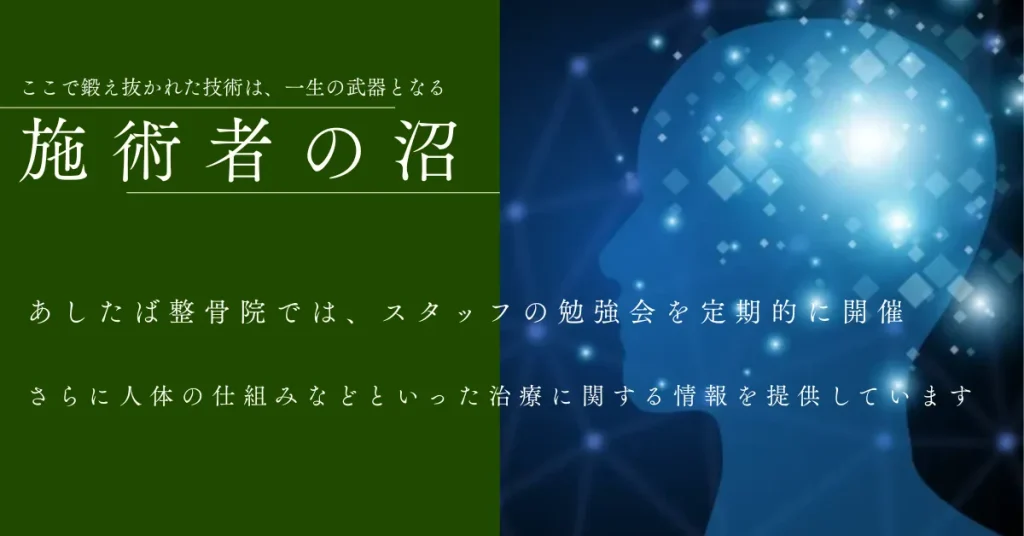看板は大きく、財布は空っぽだった
分院を退職し、自分の院を持つ
その決意を固めた久保は、これまでの“治療の旅”を形にするため、人生最大の挑戦に踏み出した。
だが、「開業する」という現実は、想像以上に苛烈だった。
― 店舗を探す。だが、どこも借りられない ―
物件を探し始めた久保に最初に突きつけられたのは、“信用の無さ”だった。
どの不動産屋でも、名刺を出せば一瞬沈黙が流れ、「開業予定の方ですね」と苦笑される。
家も買ったことがない。保証人も頼りにくい。資金も潤沢ではない。
「何も持っていない人間が、何かを始める」ということの厳しさを、これほど突きつけられたことはなかった。
それでも、足で探し、断られ、また探す。
ようやく見つけたのは築年数が古く小さな物件だったが、それでも、予想を大きく上回る初期費用が必要だった。
しかし、直感的に「ここしかない」と感じた。
そして、決めた。
「やるしかない。ここが、自分の場所だ」
看板は大きかった。
不安も大きかった。
でも、「自分がここにいる」と叫ぶように、その看板を掲げた。
「久保整骨院」最初は久保の苗字が院名だった。
2001年11月、千葉の一角に、小さな治療院が産声を上げた。
スタッフは久保と受付の女性2名。
3人だけの、小さな出発だった。
期待と現実のギャップ

開業初日。
来院した患者は、6名だった。
静まり返る院内に、壁の時計の針の音がよく響いた。
だがその6名の中に、分院長時代に遠くから通ってくれていた患者の顔があった。
その姿を見たとき、久保は目頭が熱くなるのを感じた。
少しずつ、口コミで患者が増えていく。
半年後の5月になる頃には、予約帳はびっしりと埋まっていた。
久保と、鍼灸学校時代の同期で最も見識が深く、技術も抜群だった立川目さんが途中から参画してくれて施術を担当。
1時間に4人×8時間×2人=64人。
それを毎日続ける生活が始まった。
この時期、久保の頭痛は、もはや完全に制御できていた。
決して理論が完成していたわけではない。
だが、試行錯誤の中で明らかな“パターン”を見出していた。
それは、誰よりも多くの失敗と体験を積んだ久保にしかできない治療だった。
― しかし、お金が残らない ―
「これだけ来院があって、なんで通帳が増えないんだろう…?」
帳簿を開き、愕然とする。
患者は多く、結果も出ているのに、まったくお金が残らない。
高度な施術を、健康保険の一部負担だけで提供していた。
1人ひとりに時間も手間もかける。
やればやるほど、赤字に近づいていた。
給与を払い、家賃を払い、材料費を払い、そして自分の手元には、何も残らない。
「なにかが、おかしい」
だが、その“なにか”が何なのか、久保にはまだわからなかった。
そんなある日、ある整骨院の先輩がこう声をかけてくれた。
「久保くん、そろそろ“経営”も勉強したほうがいいよ」
その一言で、久保はようやく気づく。
「治すこと」と「経営すること」は、まったく別の知識と技術が必要なのだ。
その後、経営セミナーに参加し、本や資料に目を通す。
収益構造、原価率、価格設定、理念と経営――
それまで施術に全てを注いできた久保にとって、それは全くの未知の世界だった。
だが、「治すこと」に負けないくらい、「届けること」が大切だという確信も、少しずつ芽生えてきた。
もちろん、今思えばすべてが未熟だった。
ただ“経営者っぽい雰囲気”を漂わせていただけ。
理念も戦略も、理解した気になっていただけ。
けれど、嵐はそんな“なんちゃって経営者”をあざ笑うように、やってきた。
久保は、これまでで最大の試練を迎えることになる―