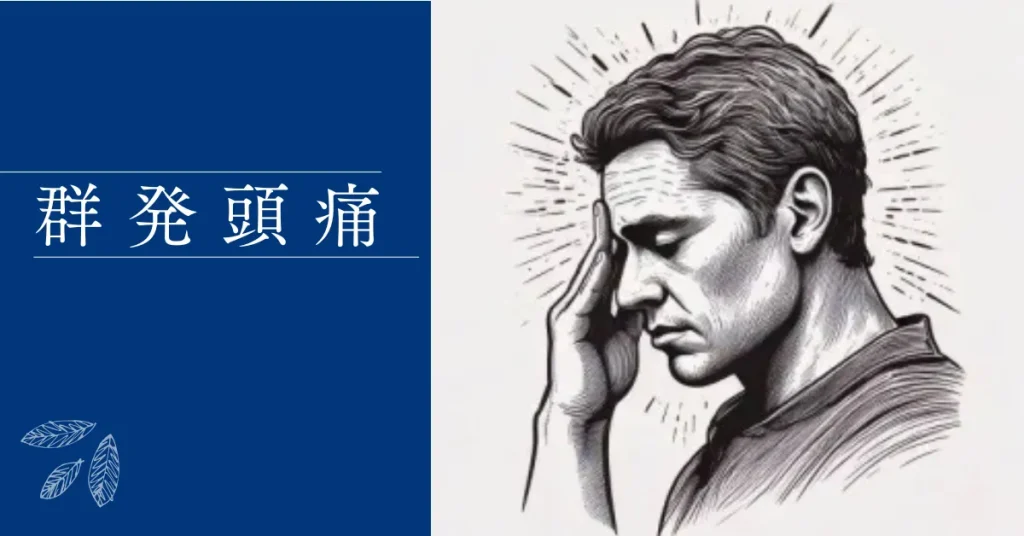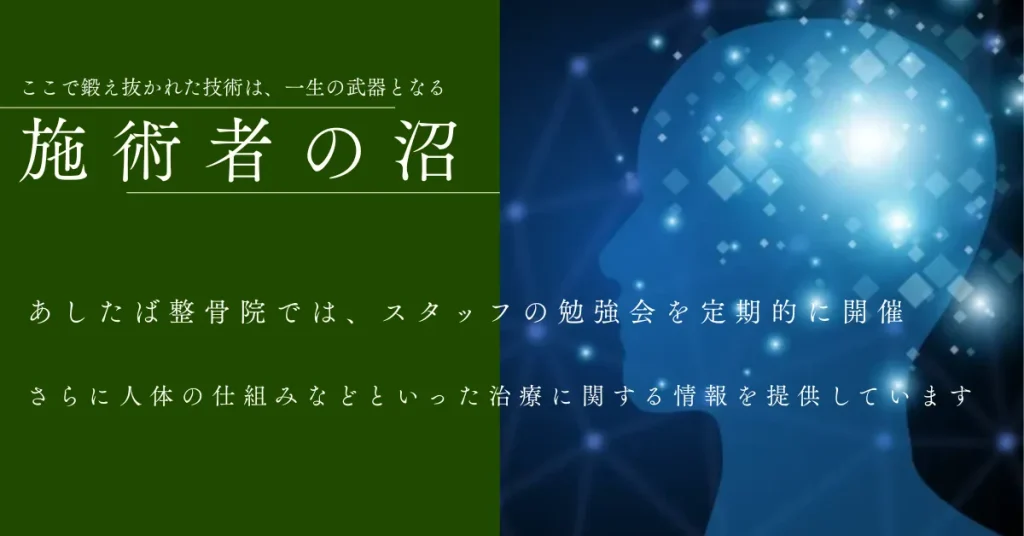動かぬ時間、消えかけた灯
2011年。
あしたば整骨院は開業から10年目を迎えていた。
経営は相変わらずの低空飛行。
患者には「評判の整骨院」と映っていたかもしれない。だが、実際には多くの課題を抱えていた。
スタッフは何人も入れ替わり、組織としての安定感は乏しかった。
特殊な施術を行っていたため、理論が十分に整っていない段階では再現性がなく、**「久保だけが治せる院」**という属人的な構造に陥っていた。
それでも、院としての“かたち”は保たれていた。
自らの手で築いた施術の原型と、それを支える少しの物販収益――
**「何とかやれている」**という薄氷の上を、静かに歩いていた。
そんなある日の午後、地鳴りと共に、その“かたち”は一瞬で崩れ去った。
2011年3月11日 14時46分――
東日本大震災。

午後の診療が始まったばかりの院内を、突如として激しい揺れが襲った。
スタッフに「患者さんを守って」と声をかけ、咄嗟に行動できたのは、久保自身も驚くほど冷静だった。
古びた建物はギシギシと音を立てながらも、崩れはしなかった。
落下したのは、サプリメントの空容器がひとつだけ。
物理的な被害は、ほとんどなかった。
しかし――
本当の試練は、そこから始まった。
午後の予約は全キャンセル。
翌日も、その翌週も、電話は鳴らなかった。
あの揺れ以降、人々の優先順位は「治療」ではなくなっていた。
日本全体が喪に服し、不安に飲まれていた。
そして、予約帳の予定が、白紙になったままの時間が、数ヶ月にわたり続いた。
迫る現実、削れていく日常
予約制に移行していた院にとって、これは致命的だった。
かつて自由来院の頃には、2時間待ちになることもあり、
「ここはディズニーランドかよ」と冗談まじりに叱られたこともある。
その反省から、予約制にした。
だが今や、その予約枠がぽっかりと空白のままなのだ。
固定費は出ていく。
スタッフに給与を出さなければならない。
しかし、来院者がほとんどいない。
当時の久保には、「非常時に備える資金」など残っていなかった。
「このまま、店を閉めなければならないのか」
本気で、そう思った夜もあった。
空白の時間がくれたもの
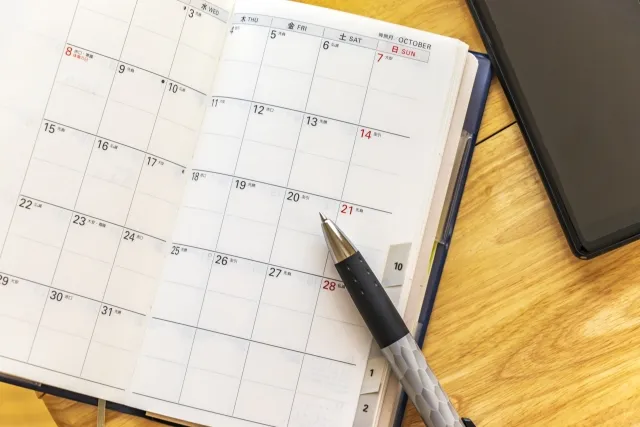
だが、皮肉なことに、この“空白の時間”こそが、最大のギフトとなった。
現場に追われない日々。
ふと、手を止めて自分の施術を見直す時間が生まれた。
本を読み、資料をあさり、仮説を立て、施術に試す。
少ない来院者を相手に、丁寧に検証を繰り返す日々。
「どの刺激が、どんな反応を起こすのか」
「からだが反応する“適正な時間”とは何か」
長くやれば良いわけではない。
強ければ効くわけでもない。
“ちょうどいい”刺激量とタイミングがある。
この時期に突き止めた“時間と質の関係”は、
のちの治療理論の柱となっていく。
誰にも頼れない状況だったからこそ、
誰にも流されず、自分の声だけを聴くことができた。
患者は、少しずつ、戻ってきた。
そしてそのときには、久保の中で何かが変わっていた。
「技術だけでは、院は残らない」
「再現性と仕組みが無ければ、誰も幸せにできない」
この気づきは、やがて“治療家”から“経営者”へと踏み出すきっかけになる。
それは、すべてを奪われたと思った試練の中で、唯一燃え残った火だった。