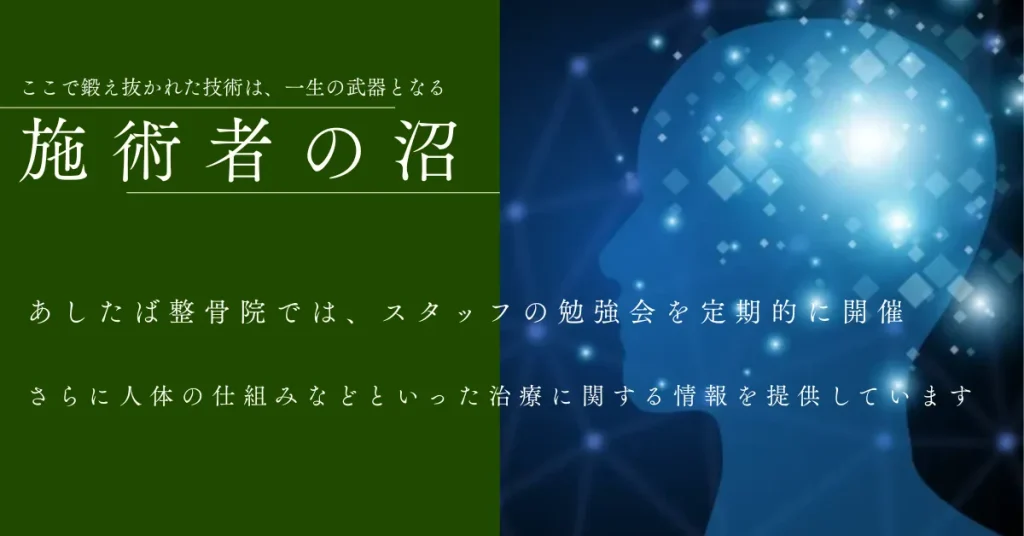「治してくれる人」との出会い ~冒険への呼びかけ~
骨が折れてるんじゃないか…… ~冒険への呼びかけ~
それは、小学5年の秋。
落ち葉が風に舞い始めた頃のことだった。
掃除の時間、下足場のすのこを雑巾がけしていた久保は、ふいに足を滑らせ、右足首を強くひねった。
最初は「またか」と思った。これまでも、関節の痛みや重だるさには慣れていた。
だが、この日は違った。
足首はすぐに腫れ上がり、体重をかけるたびに鋭い痛みが走る。
帰り道、片道15分の通学路を、足を引きずりながら1時間以上かけて歩いた。
何とか自宅にたどり着いたものの、腫れはひどくなる一方だった。
「もしかして、骨が折れてるんじゃないか……」
いつもなら痛みは黙ってやり過ごす久保だったが、このときばかりは強い不安に襲われていた。
初めての整骨院 ~冒険への呼びかけ~

その日の夕方、母が連れて行ってくれたのは、近所にある街の整骨院だった。
病院ではない――それがどんな場所なのか、久保は知らなかった。
整骨院という言葉自体、彼にとっては初耳だった。
木の香りがふんわりと漂い、やわらかな照明が迎えてくれるその空間は、彼が知る「医療機関」とはどこか違っていた。
ソファに座って問診表を記入しながら、久保は言いようのない緊張を感じていた。
心の中には、いつもの疑念がよぎっていた。
――また、「気のせい」と言われるんじゃないか。
――「骨に異常がなければ問題なし」と、片づけられるんじゃないか。
これまで、さまざまな不調を抱えながらも、病院へ通うことはほとんどなかった。
「どうせ原因はわからない」
「言っても仕方がない」
いつしかそんな思いが先に立つようになっていたからだ。
だが、この日だけは、違っていた。
寄り添う温もり、目覚めの瞬間 ~冒険への呼びかけ~
現れた施術者は、久保の目を見て、穏やかに微笑んだ。
「今日はよく来たね。ちょっと診せてね」
やわらかい手が、腫れた足首にそっと触れる。
皮膚の熱、腫れの広がり、可動域をていねいに確かめながら、言葉をかけてくれる。
「骨は折れてないよ。靭帯がちょっと伸びてるだけだね」
その一言を聞いたとき、久保の胸の奥に張り詰めていた糸が、ふっと緩んだ。
“見てもらえた”“わかってもらえた”――それだけで、身体が少し軽くなるような気がした。
包帯でしっかり固定され、氷で冷やしながらの処置。
施術者は、今後の過ごし方や注意点まで、母と一緒にわかりやすく説明してくれた。
それは、これまで久保が経験したことのない「寄り添い」だった。
治療が終わる頃には、久保の心の中に、不思議な灯りがともっていた。
「身体が治る」って、こんなふうに感じられるものなんだ。
「触れることで、人の痛みがやわらぐ」って、こんなに尊いことなんだ。
機械の音も、白く冷たい診察室もない。
でもそこには、「人が人に向き合う」という温もりがあった。
帰り道、まだ腫れの残る足を引きずりながらも、久保の心は軽かった。
施術者のまなざしと、包帯の温かさが、何度も頭の中によみがえった。
「もし、自分があの人のように“治す側”になれたら――」
そんな思いが、初めて芽生えた。
もちろん、足首の痛みはしだいにおさまっていった。
だが、それとは対照的に、以前から続く関節の違和感や目の奥の痛みは、相変わらず残ったままだった。
「全部が治ったわけじゃない。でも、“良くなる”ことは、たしかにある」
子どもながらに、彼はその手応えを感じていた。
“適切な処置”を受けることの大切さ――それを、初めて知った瞬間だった。
まだ言葉にはできなかったが、久保の中で何かが変わり始めていた。
それは、人生を方向づける最初の呼びかけだった。