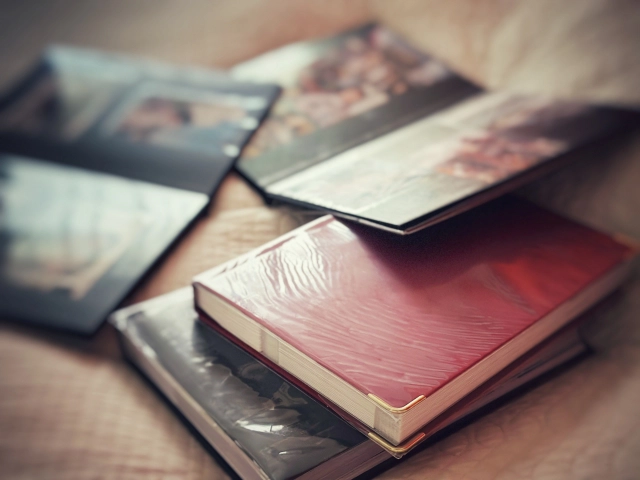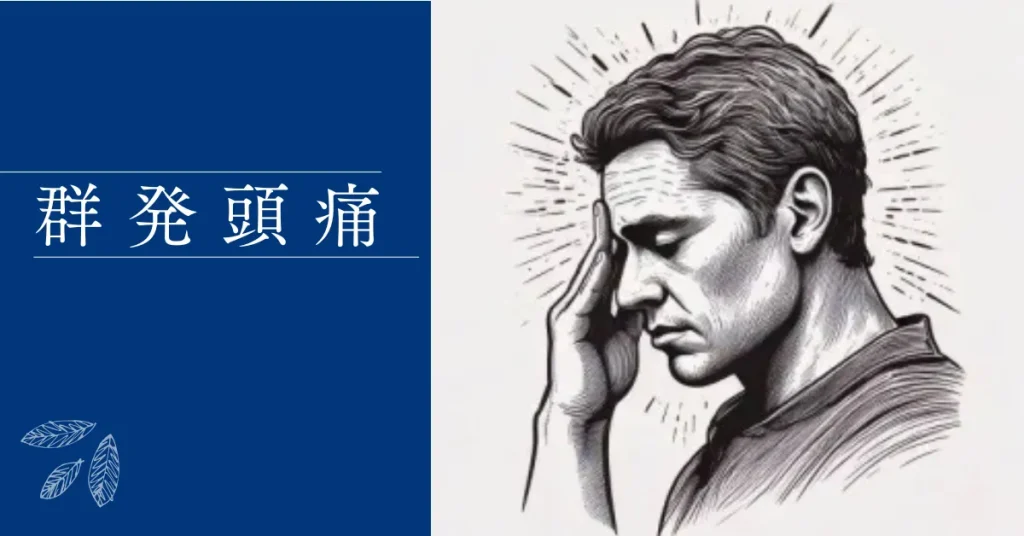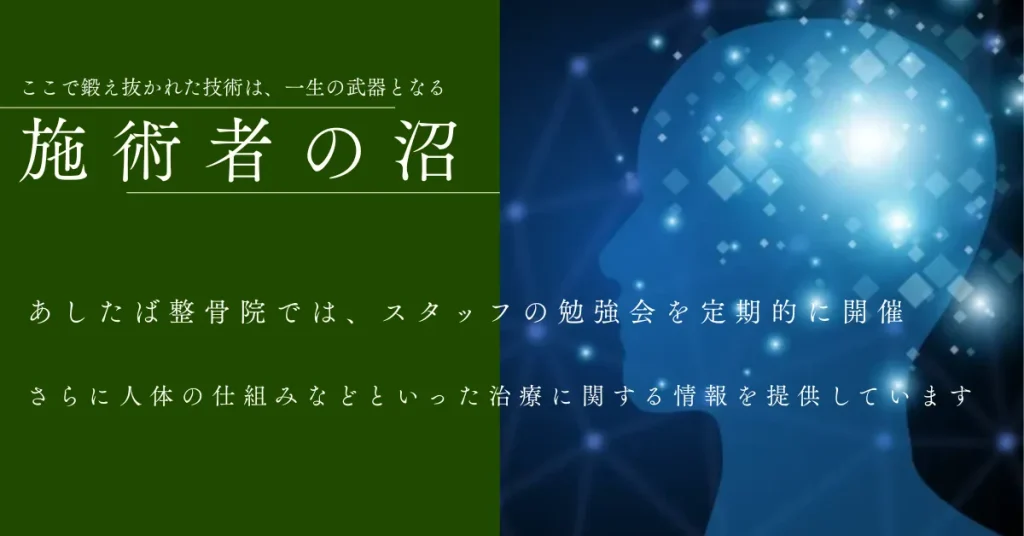日常世界(Ordinary World) -その痛みは、誰にも見えなかった
その痛みは、誰にも見えなかった
久保が“異変”を感じたのは、小学4年生の冬の日だった。
前夜に降った雪が白く積もる登校の道。ふだんと変わらない帰り道を歩いていたそのとき、不意に足元をすくわれ、背中から氷の地面に叩きつけられた。
呼吸が止まるような衝撃。けれど、すぐに起き上がれたことで「大したことはない」と思い込んだ。
だが、その日を境に、彼の身体は少しずつ音を立てて軋み始めた。
最初に異変が出たのは、左の股関節だった。
次に右の膝、背中の張り、そして首や肩の違和感が広がっていく。
「成長痛かもしれませんね」――そう言われても、痛みは日を追うごとに鋭さを増していった。
加えて、小学5年生の頃からは、「それ」としか言えないほどの、謎の激痛が彼を襲うようになった。
左目の奥が突き刺されるように痛み、呼吸も思考も奪われる。群発頭痛――のちにそう名付けられるこの症状に、彼は名前がつく前から耐え続けていた。
誰にも理解されない。
病院でCTやレントゲンを撮っても「異常なし」。
医師の表情は困惑から無関心へと変わり、やがて「気のせいかもしれませんね」とさえ言われた。

学校でも、状況は変わらなかった。
運動が得意ではなかった久保は、体育の授業が苦手だった。
関節がこわばる朝、痛みを抱えながら動きの悪い身体で授業に出ると、「手を抜いている」と言われた。
運動会では走りきれず、息を切らして立ち尽くす彼を、クラスメイトは冷ややかに見ていた。
「怠けてるんじゃないの?」「やる気がないんだろ?」
その言葉は、誰よりも自分自身を刺した。
やがて久保は、痛みを訴えることをやめた。
誰も信じてくれないのなら、信じてもらおうとするのは無意味だ――それが、彼なりの結論だった。
久保は内向的な少年だった。
もともと、教室の輪の中で騒ぐよりも、砂場で独り遊びに夢中になるような子どもだった。
勉強が特別得意というわけでもない。ただひとつ、夜空や宇宙、自然の仕組みにだけは強く惹かれた。
天文図鑑を読み、星座を覚え、惑星の名前を呟いては、頭の中で遠い星の配置を描いた。
自然科学の本を開いては、「この世界には、まだ見えていない仕組みがある」ことに、妙な安心を覚えていた。
目に見えないけど、確かに存在するものがある -その痛みは、誰にも見えなかった
――それが、彼の心を支えていた。
だからこそ、自分の中にある“痛み”も、どこかに原因があるはずだと信じたかった。
けれど、現実の世界は、目に見えないものを「存在しない」と切り捨てる場所だった。
どこでも、久保は「大丈夫」と言い続けるようになった。
心配をかけたくない。信じてもらえないのが怖い。
布団の中で身体を丸めて、暗闇のなか、再び来るであろう痛みに備えるしかなかった。
「どうして、誰もわかってくれないんだろう」

そう呟いた言葉が、口の中で消えていく。
宇宙の果てを想像して心を落ち着けながらも、現実の孤独は、どこまでも重く、静かに彼を覆っていた。
――それが、久保にとっての“普通”の毎日だった。